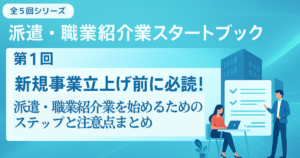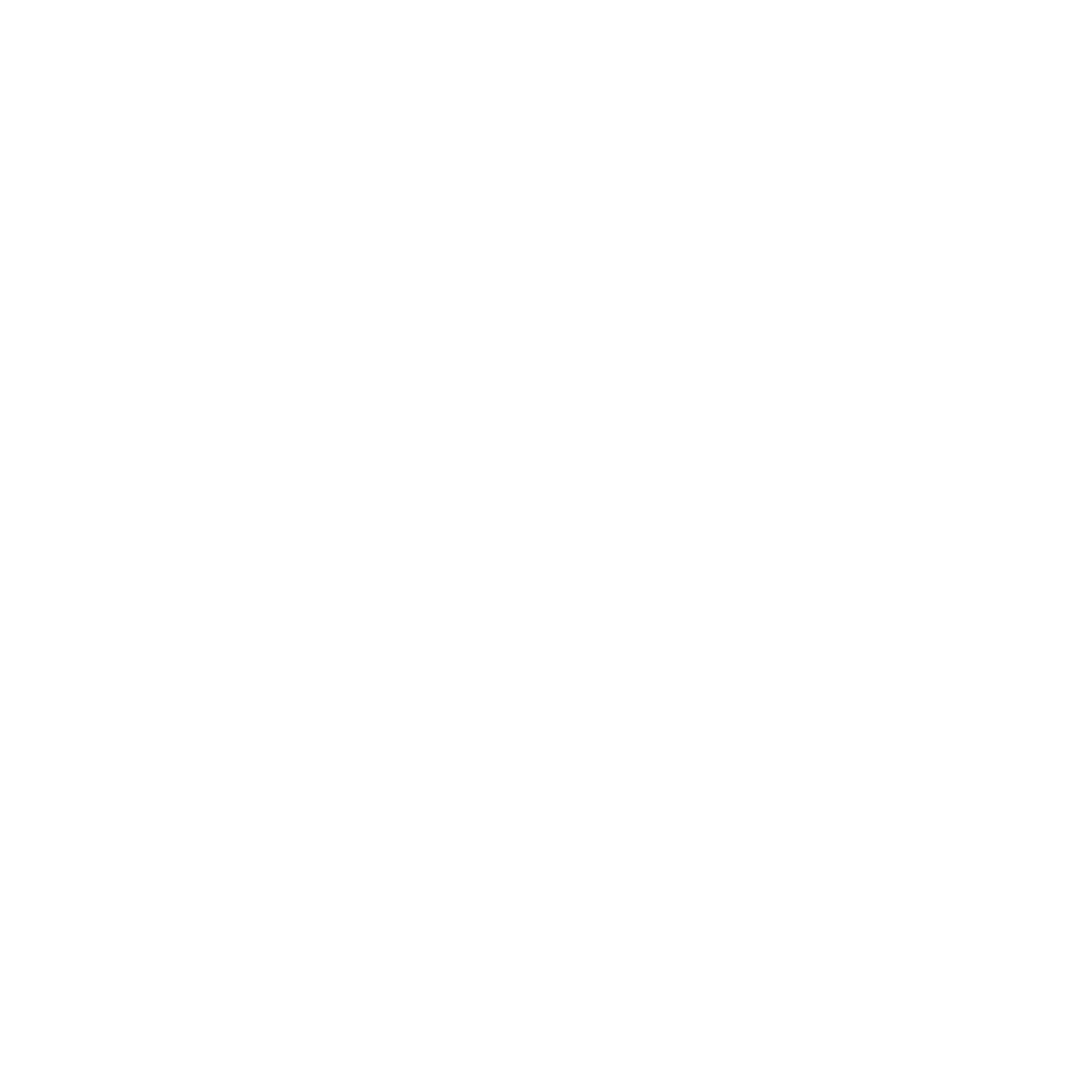【派遣業編】許可取得の「落とし穴」5選|申請でつまずかないためのチェックポイント!
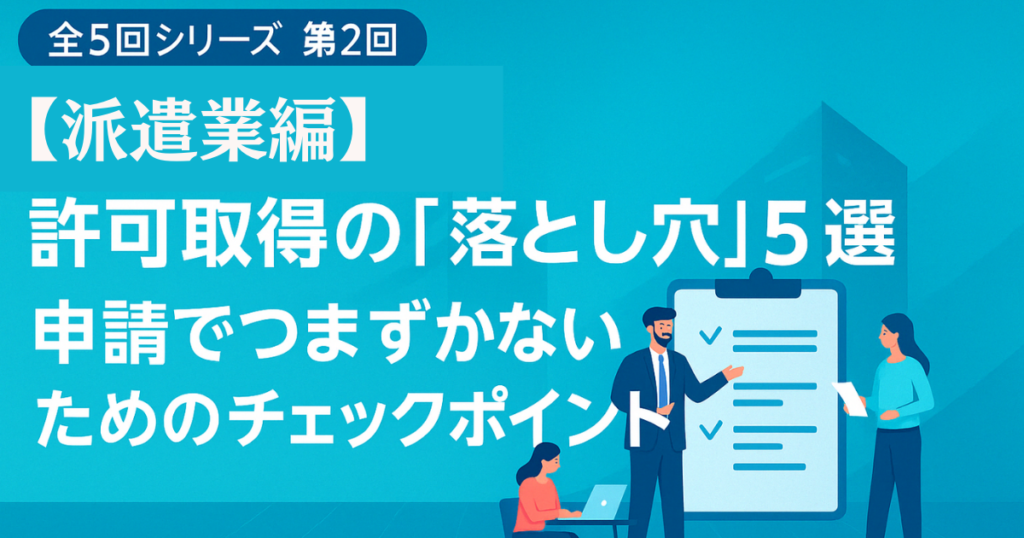
目次
はじめに
派遣業の許可申請を検討するにあたって、まず押さえておくべきことは、
「派遣とはどのような働き方か」という基本構造です。
これを知らずにビジネスを始めてしまうと、思わぬ法令違反や不適切な運用に陥るリスクもあります。
まずは派遣の仕組みとルールの概要を整理しましょう。
「はじめての許可取得!派遣・職業紹介業スタートブック」
💡このブログは
「はじめての許可取得!派遣・職業紹介業スタートブック」全5回シリーズの第2回です。
派遣・職業紹介の違いから許可取得、運営時の注意点まで、順を追ってわかりやすく解説していきます!
派遣とは? まず押さえておきたい派遣ビジネスの基本
「派遣業を始めたい」と考える際に、まず理解しておくべきことは、派遣という働き方の法的構造です。
🔹 派遣のしくみ(誰が雇用主?誰が指示する?)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 雇用契約 | 派遣元(あなたの会社)と派遣労働者が結びます |
| 指揮命令 | 派遣先企業が行います(職務指示など) |
| 給与の支払い | 派遣元が行います(派遣先は派遣料金として支払う) |
| 社会保険・労災保険 | 派遣元が加入させます |
| 有給休暇の管理・付与 | 派遣元が行います(派遣先ではありません) |
✅ 派遣労働者は“あなたの社員”として雇い入れ、派遣先に「貸し出す」仕組みです。
労務管理や契約管理の責任は派遣元にあります。
🔹 派遣を行ってはならない業務・ルールの例
- 港湾運送業務・建設業務・警備業務・医療関係の業務など(一部例外あり)
- 日雇い派遣は禁止(60歳以上、昼間学生、年収500万円以上の副業者など例外あり)
- 離職後1年以内の元従業員を元の勤務先に派遣することは禁止(60歳以上の定年退職者を除く)
- グループ企業派遣の8割規制:グループ企業間での派遣は全体の8割を超えてはならない
- 事業所単位・個人単位の派遣期間制限:原則3年(これがいわゆる「3年ルール」)
📌 このように、派遣には多くのルールが存在し、安易にスタートすると法令違反のリスクもあるため、
事前の知識と許可取得がとても重要なのです。
許可申請でつまずかないためのチェックポイント|5選
❶ 資産要件は「形式」だけでなく「安定性」も見られる
労働者派遣事業を行うためには、一定の財産的基礎が必要です。具体的には、次のような要件があります:
- 基準資産額:2,000万円以上
- 現預金:1,500万円以上(常時派遣労働者が10人以下の場合)
- 基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
しかし、単に金額を満たしていればOKというわけではありません。たとえば、決算直後に大幅な役員報酬の引き上げや、急な設備投資で純資産が減少していると、財務の安定性に疑義が持たれる場合があります。
また、会計処理のタイミングや説明資料の不足によって、形式上の要件は満たしているのに補正指示を受けるケースも見られます。
❷ 「キャリア形成支援制度」の内容が薄すぎる
派遣労働者のキャリアアップを支援するため、許可申請時には「キャリア形成支援制度」の整備が求められます。
派遣法第30条の2では、派遣元事業主に対し、教育訓練の実施と相談体制の整備義務が課せられています。厚生労働省のガイドラインでは、以下のような内容が求められています:
- 対象者の範囲と教育内容
- OJT/OFF-JTのバランス(両方が必要)
- 年次計画や実施体制
テンプレートをそのまま流用しただけでは不十分であり、自社の派遣業務の特性や職種に合わせた設計が不可欠です。計画の実現可能性や記録管理の方法まで含めて、現実的な制度設計が必要です。
❸ 責任者や代行者の「要件不備」や「選任漏れ」
労働者派遣法では、事業所ごとに「派遣元責任者」を選任することが義務付けられています(第36条)。この責任者は、次のいずれかの要件を満たす必要があります:
- 派遣事業に関する実務経験が3年以上ある
- 厚労省指定の派遣元責任者講習を修了している
さらに、「臨時の職務代行者」も事前に届出が必要であり、これを忘れていると補正の対象になります。
また、責任者が他の事業と兼任している場合、勤務日数や実務遂行能力に疑義が出ることもあるため注意が必要です。
❹ 「専ら派遣」と見なされる事業計画
■ 「専ら派遣」とは?
「専ら派遣」とは、特定の派遣先1社にのみ労働者を継続的に派遣することをいいます。「専ら派遣」を行う予定があるか、許可審査でも厳しく見られます。
■ なぜNGなの?
- 派遣労働は、臨時的・一時的な労働力の提供を前提としており、派遣先企業の“社員の代替”となるような使い方は不適切とされています。
- 企業が雇用責任を回避し、労働者保護が損なわれる構造になるためです。
■ 対応策は?
- 複数の派遣先との契約予定を明示する
- 営業活動の実績や今後の計画を具体的に示す
- 売上構成比や営業ターゲットを数値で補足
「専ら派遣」と誤解されないように、事業計画の記載は明確かつ戦略的に行うことが重要です。
❓【よくある混同】「グループ企業への派遣は8割まで」と言われることがありますが、これは同一企業グループ内の派遣に対する“8割規制”のことです。 一方、「専ら派遣」は派遣先が1社しかない場合などに適用され、グループ外でも対象になる可能性があるため、両者は別物として理解しましょう。
❺ 必要書類は「揃っていればOK」ではない
派遣業の許可審査では、「様式が揃っている」ことよりも「内容の整合性と実行可能性」が重視されます。 また、最近の審査傾向として以下のようなポイントも見落としがちなので注意が必要です:
- 就業規則は作成だけでなく「労基署への届出済み」が必要(届出印付きの写しがベスト)
- 賃貸借契約の使用目的が「事務所使用」であることが必須(住居用契約ではNG)
- 契約書・届出書類などで空欄や矛盾のある記載があると補正対象に
- 必要に応じて「実地調査(事業所確認)」が行われる (オフィス設備や備品、事業所名義の確認、看板の有無など)
派遣業の許可申請では、多くの提出書類が求められますが、形式が整っていても中身に不備や矛盾があると補正対象になります。以下は代表的な注意点です:
- 就業規則が未提出または未届出
- 雇用契約書の内容が職種や雇用区分に適していない
- キャリア形成支援制度の内容が曖昧または現実味がない
- 事業所の賃貸借契約書の名義や使用目的が不適切
■ 提出書類(代表例)
- 決算書・法人税申告書・納税証明書
- 派遣元責任者講習修了証、履歴書・住民票
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 就業規則・賃金規程(教育訓練や休業手当の規定を含む)
- 賃貸借契約書、事務所のレイアウト
- キャリア形成支援制度に関する計画書
- 個人情報管理規程、事務手引き等
- (必要に応じて)残高証明書
※この一覧は一例です。詳細・最新情報は東京労働局の提出書類一覧(PDFリンク)をご確認ください。
「様式はあるけど中身がない」状態では許可されません。内容の整合性と運用可能性を意識して整備することが重要です。
まとめ
派遣業の許可取得は、「書類を揃えるだけ」ではなく、その中身が現実的であり、法令に基づいた運用が想定されていることが重要視されます。特に、今回ご紹介した5つの落とし穴は、事前に回避可能なものばかりです。
初めて許可を申請する方は、形式面だけでなく実務運用も視野に入れ、信頼性ある体制を整えた上で臨みましょう。
次回予告
次回は、【職業紹介業編】始める前に押さえておきたい!ビジネス形態・手数料・個人情報管理の実務要点
職業紹介業を適切に運営するには、法令に基づいた手数料の設計や、個人情報保護体制の整備など、設立初期からの対応が非常に重要です。
制度の背景と実務運用の両面から解説します。
「はじめての許可取得!派遣・職業紹介業スタートブック」
💡このブログは
「はじめての許可取得!派遣・職業紹介業スタートブック」全5回シリーズの第2回です。
派遣・紹介の違いから許可取得、運営時の注意点まで、順を追ってわかりやすく解説していきます!

お困りごとやご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- こだま社労士オフィス代表 社会保険労務士
-
【社員想いの経営者を、労務の確かな土台で支える】
企業価値の源泉である「人」に焦点を当て、採用、成長、定着といった人的資本経営の最重要課題を解決に導く社会保険労務士です。
【当オフィスの3つの強み】
①専門性の高い従業員を抱える企業様の課題解決:スタートアップ、医療クリニック、派遣・職業紹介業などの高い専門性 を持つ従業員の労務管理に強みを持っています。給与制度の不備が即退職に繋がるような課題に対し、細心の注意を払い、慎重かつ正確な対応を重視します。
②代表社労士による直接対応:代表社労士が直接、責任をもって対応し、質の高いアウトプットを保証します。
③業務を止めない定額(サブスク)サポート:ご相談のたびに都度見積もり・依頼判断は不要。業務を止めずに確実なサポートを提供し、経営効率を高めます。私たちはアウトソーシング先ではなく、お客様の経営判断を支援する戦略的パートナーとして事業の「安心」と「成長」を支えます。
まずはお気軽にお問合せください。
最新の投稿
 お知らせ2025.12.15年末年始休業のお知らせ
お知らせ2025.12.15年末年始休業のお知らせ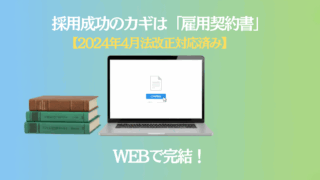 法改正2025.09.26採用成功のカギは「雇用契約書」にあり!2024年4月法改正への対応と業務効率化の秘訣
法改正2025.09.26採用成功のカギは「雇用契約書」にあり!2024年4月法改正への対応と業務効率化の秘訣 派遣事業2025.08.26【速報】派遣労働者の同一労働同一賃金 ― 労使協定方式の賃金水準(令和8年度)局長通達
派遣事業2025.08.26【速報】派遣労働者の同一労働同一賃金 ― 労使協定方式の賃金水準(令和8年度)局長通達 助成金2025.08.132025年10月の最低賃金改定額【確定版】|月給者の確認方法と助成金活用法
助成金2025.08.132025年10月の最低賃金改定額【確定版】|月給者の確認方法と助成金活用法