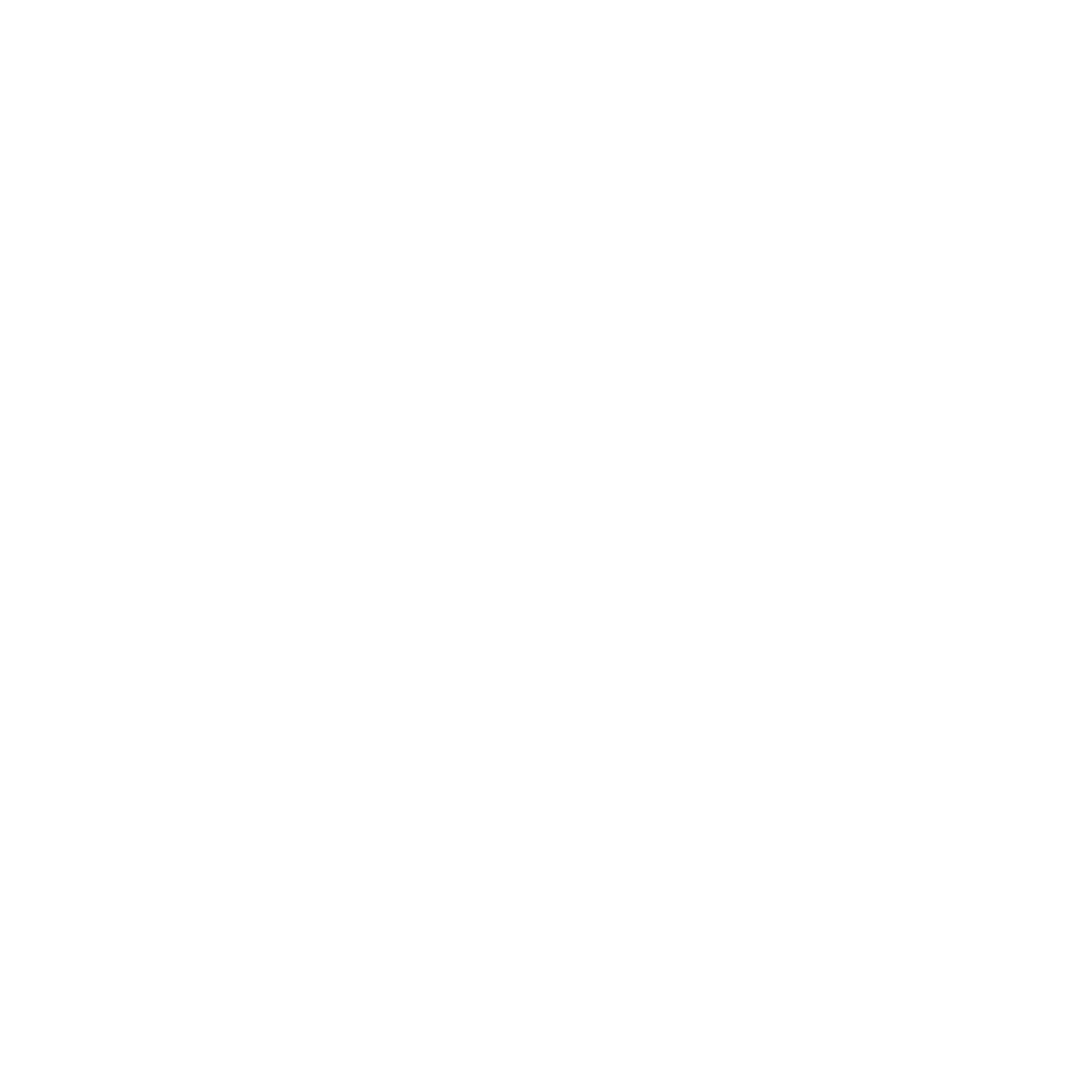採用成功のカギは「雇用契約書」にあり!2024年4月法改正への対応と業務効率化の秘訣
「人を増やしたいけれど、雇用契約書の作成や手続きが煩雑で時間がかかる…」「法改正への対応は大丈夫だろうか…」
採用活動を積極的に行っている企業の担当者様や経営者様は、そんなお悩みを抱えていませんか?
雇用契約書は単なる事務手続きではありません。内定者の入社意欲を高め、入社後の定着率を左右する重要なツールとなり得ます。
- 入社意欲の向上
- 労働条件が明確に記載された雇用契約書は、企業側の誠実さを示し、内定者に安心感を与えます。
- ミスマッチの防止:
- 業務内容や勤務地、給与体系などを正確に明示することで、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防ぎます。
- 早期離職の防止
- 入社後のトラブルを未然に防ぎ、従業員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高めることで、定着率向上に繋がります。
2024年4月1日の労働条件明示のルール変更により、雇用契約書はますます重要かつ複雑になっています。しかし、この法改正をチャンスと捉え、効率的な仕組みを構築することで、貴社の採用活動を強力に後押しできます。

この記事では、雇用契約書作成時に知っておくべき法改正のポイントから、当事務所が提供する業務効率化の秘訣まで、採用を成功に導くためのすべてを解説します。
目次
雇用契約書は「言った、言わない」のトラブル防止に不可欠
雇用契約書は、単なる事務手続きではありません。労働時間、賃金、休日など、働く上での基本的なルールを明確にし、企業と従業員双方の権利と義務を定める、非常に重要な書類です 。口頭での約束は、後々のトラブルに発展する可能性が高いため、書面での取り交わしが不可欠です 。
特に2024年4月1日の法改正では、労働条件明示のルールが追加・変更されました 。
- 就業場所・業務内容の「変更の範囲」の明示
- これまでは雇い入れ直後の就業場所や業務内容を明示すれば十分でしたが、法改正により、将来的に変更が見込まれる可能性のある「変更の範囲」を書面で明示することが義務付けられました 。
- 有期労働契約における「更新上限」と「無期転換ルール」の明示
- パート・アルバイト・契約社員・定年再雇用者などの有期雇用契約では、契約締結時と契約更新のたびに、更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数の上限)を明示しなければなりません 。
- また、有期労働契約が通算5年を超える場合、従業員の申込みにより無期雇用に転換される「無期転換ルール」があります 。今回の改正で、無期転換申込権が発生するタイミングで「無期転換を申し込める機会があること」と「無期転換後の労働条件」を明示することが義務付けられました 。
雇用契約書の記載例:正社員・パートの具体的なポイント
法改正の内容を踏まえ、実際の雇用契約書にはどのように記載すればよいのでしょうか。ここでは、特に重要な記載例をいくつかご紹介します。
就業場所・業務内容の「変更の範囲」明示(全労働者対象)
2024年4月改正の最大のポイントは、「今後の見込みも含め、当該労働契約の期間中における就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」を書面により明示する義務が課された点です
この「変更の範囲」を明示することは、以下の点で採用成功のカギとなります。
- 合意の明確化とトラブル防止: 変更の範囲が明示されることで、就業場所・従事すべき業務が限定されていることが明確になり、職種・勤務地限定の合意が書面による明示の合意として認定されやすくなります。これは、労働契約の解釈として法的に認められやすくなることを意味します 。
- 専門人材の確保: 職務内容を明確に限定することで、入社後に想定外の業務を命じられる不安を解消し、専門性を重視する人材の確保に繋がります。
【記載例】
| 区分 | 雇入れ直後 | 変更の範囲 |
| 限定なし | ○○営業所 | 会社の定める営業所 |
| 勤務地限定 | 本社 | 本社(変更なし) |
| 職種限定 | 開発業務 | 開発業務(雇入れ直後の従事すべき業務と同じ) |
パート・アルバイトにおける「同一労働同一賃金」に対応した雇用管理
同一労働同一賃金とは、同一企業における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
正社員とパート・アルバイトの待遇差(賃金や賞与など)を設ける際には、その差が不合理ではないことを説明できなければなりません。この待遇差の合理的な根拠となるのが、「業務の内容」「責任の程度」、そして「異動の有無・範囲」といった、雇用契約書に明記する「変更の範囲」の限定性です。
正社員の雇用契約書とパート・アルバイトの雇用契約書で、「変更の範囲」を明確に区別し記載することが、同一労働同一賃金に対応した雇用管理に繋がります。
【正社員とパートの「限定性」の比較記載例】
| 区分 | 業務内容(変更の範囲) | 就業の場所(変更の範囲) |
| 正社員 | 会社の定める業務 | 会社の定める場所 |
| パート・アルバイト | ○○補助業務 | ○○営業所 |
ポイント: 正社員は「限定なし」とすることで広範な責任や異動の可能性を負う(その分、待遇が厚くなる)。一方、パート・アルバイトは勤務地や職務を「限定あり」とすることで、待遇差の合理的な説明がしやすくなります。
【重要】
パート・アルバイトの雇用契約における「変更の範囲」の定めは、あくまで企業の雇用実態に基づくものです。パート・アルバイトでも正社員と同様に広範な責任や業務を担う場合は、「変更の範囲」に限定を設けない記載とすることも可能です。貴社の実態と労務方針に合わせて定める必要があります。
有期雇用契約の「更新上限」と「無期転換ルール」
「1年ごとの更新制」など有期雇用契約を締結する場合、2つの明示がかならず必要です。
①契約更新の上限の明示
有期雇用契約の締結と契約更新のタイミングごとに、通算契約期間または更新回数の上限がある場合には、その内容を明示しなければなりません 。
【記載例】
| 項目 | 記載例 |
| 通算契約期間 | 契約期間は通算2年を上限とする |
| 更新回数 | 契約の更新回数は3回まで |
②無期転換ルールに関する事項の明示
- 有期雇用契約が同一の使用者との間で通算5年を超えて更新された場合、従業員からの申込みにより期間の定めのない労働契約(無期契約)に転換されます。
- 従業員から申込みがあった場合、使用者はこれを拒むことはできません。無期労働契約が成立します 。
- この無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込める機会と無期転換後の労働条件を書面により明示することが義務付けられています。
【無期転換ルールに関する記載例】
| 項目 | 記載例 |
| 無期転換申込機会 | 本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。 |
| 無期転換後の労働条件 | 原則同一条件の場合: 無期転換後の労働条件は本契約と同じ 変更がある場合: 無期転換後は、労働時間を○○、賃金を○○に変更する |
【当事務所の強み】雇用管理を効率化する電子締結サービス
「法改正への対応も重要だけど、書類作成や手続きに時間をかけている余裕はない…」
そのようなお悩みを抱える企業のために、こだま社労士オフィスでは、顧問契約いただいているお客様に、雇用契約書の作成から締結までをオンラインで完結できるサービスを提供しています。
雇用契約書電子化のシンプルな3ステップ
- ステップ1:雇用契約書の作成とタスク発行
- 企業ごとにカスタマイズした雇用契約書フォーマットを作成し、システムを通じて従業員に公開します 。
- ステップ2:従業員による合意
- 従業員はメール通知を受け取り、PCやスマートフォンから専用マイページにログイン。そこで契約内容を確認し、「合意する」ボタンをクリックするか、署名を入力することで、簡単に合意手続きを完了できます 。
- ステップ3:文書番号自動付番とデータ管理
- ・合意済みの契約書には、自動で文書番号が付番されシステム上で安全に保管されるため、紙の書類管理から解放されます。
・企業の電子印鑑を登録する機能もあります。
【電子締結サービスの法的根拠】
労働条件の明示は書面による交付が原則ですが、労働者が希望した場合は、電子メール等の電磁的方法による明示も法的に認められています。
当事務所のサービスは、この法規定に則り、効率的かつ安全に契約締結をサポートします。
まとめ
雇用契約書は、単に書類を作成するだけでなく、法改正に準拠し、効率的に運用することが、優秀な人材の確保と定着に繋がります。雇用契約書には、職種限定合意の有無や同一労働同一賃金、有期雇用契約の適切管理、無期転換ルールなど重要なポイントが詰まっています。
こだま社労士オフィスでは、雇用契約書の作成・見直しから電子締結まで、貴社の採用活動と労務管理をトータルでサポートします。

ご相談はいつでもお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- こだま社労士オフィス代表 社会保険労務士
-
【社員想いの経営者を、労務の確かな土台で支える】
企業価値の源泉である「人」に焦点を当て、採用、成長、定着といった人的資本経営の最重要課題を解決に導く社会保険労務士です。
【当オフィスの3つの強み】
①専門性の高い従業員を抱える企業様の課題解決:スタートアップ、医療クリニック、派遣・職業紹介業などの高い専門性 を持つ従業員の労務管理に強みを持っています。給与制度の不備が即退職に繋がるような課題に対し、細心の注意を払い、慎重かつ正確な対応を重視します。
②代表社労士による直接対応:代表社労士が直接、責任をもって対応し、質の高いアウトプットを保証します。
③業務を止めない定額(サブスク)サポート:ご相談のたびに都度見積もり・依頼判断は不要。業務を止めずに確実なサポートを提供し、経営効率を高めます。私たちはアウトソーシング先ではなく、お客様の経営判断を支援する戦略的パートナーとして事業の「安心」と「成長」を支えます。
まずはお気軽にお問合せください。
最新の投稿
 お知らせ2025.12.15年末年始休業のお知らせ
お知らせ2025.12.15年末年始休業のお知らせ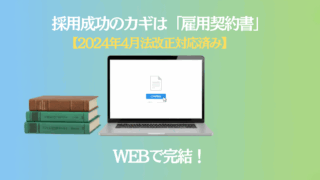 法改正2025.09.26採用成功のカギは「雇用契約書」にあり!2024年4月法改正への対応と業務効率化の秘訣
法改正2025.09.26採用成功のカギは「雇用契約書」にあり!2024年4月法改正への対応と業務効率化の秘訣 派遣事業2025.08.26【速報】派遣労働者の同一労働同一賃金 ― 労使協定方式の賃金水準(令和8年度)局長通達
派遣事業2025.08.26【速報】派遣労働者の同一労働同一賃金 ― 労使協定方式の賃金水準(令和8年度)局長通達 助成金2025.08.132025年10月の最低賃金改定額【確定版】|月給者の確認方法と助成金活用法
助成金2025.08.132025年10月の最低賃金改定額【確定版】|月給者の確認方法と助成金活用法